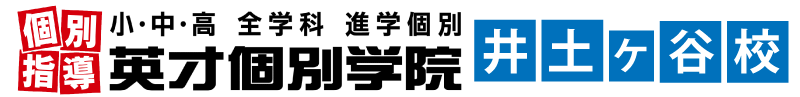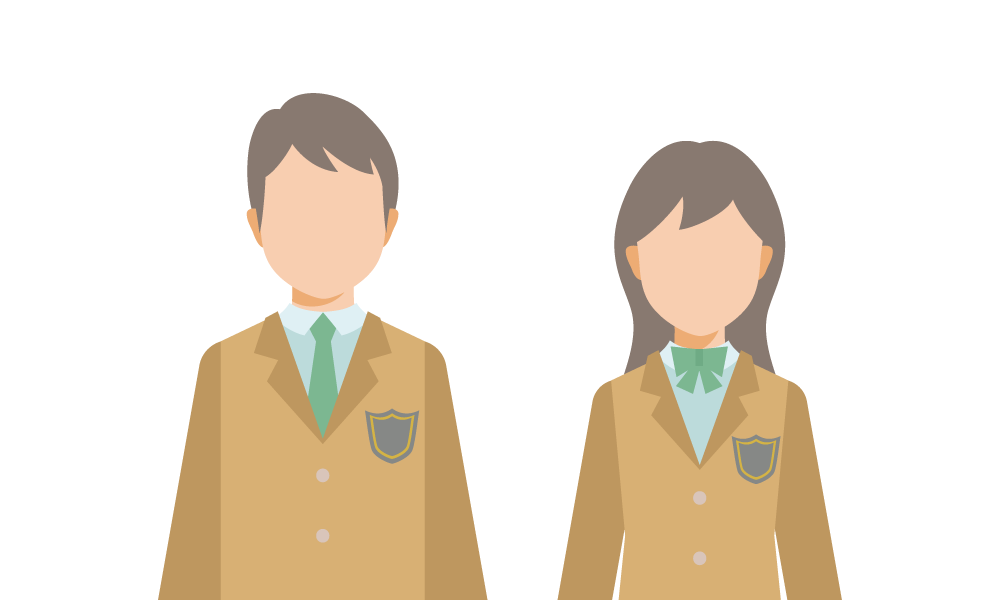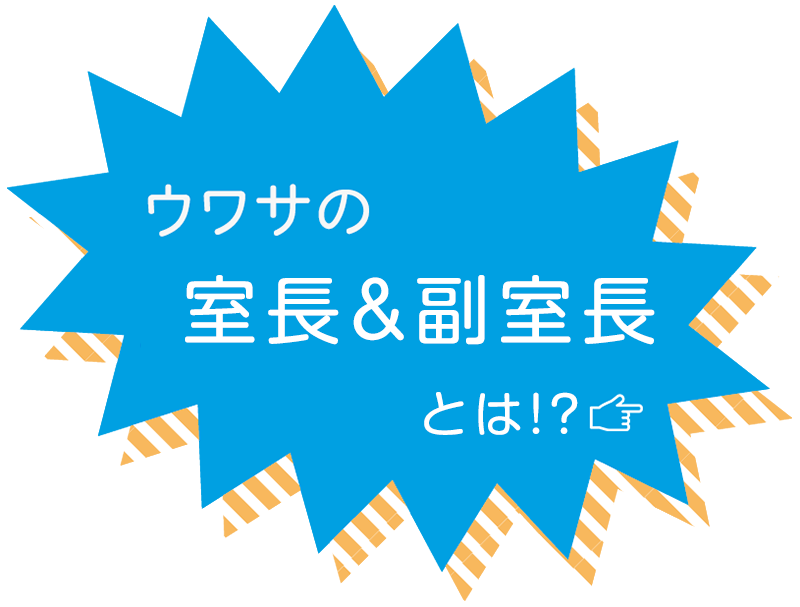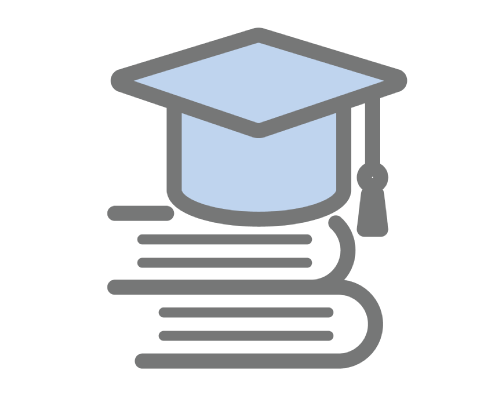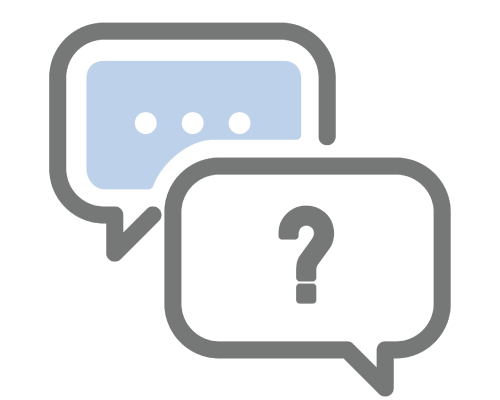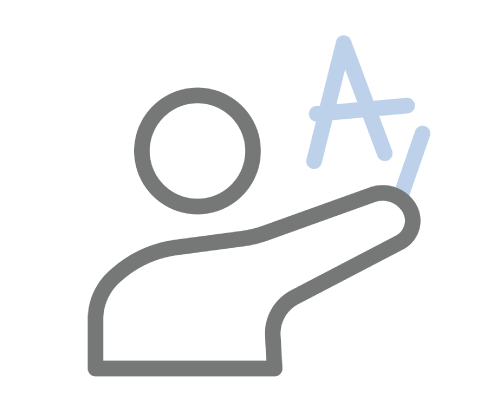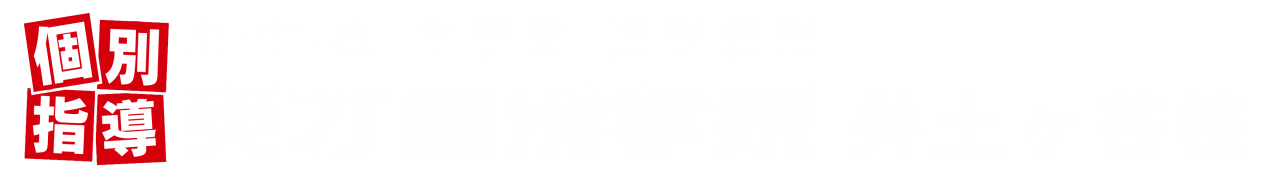ナンデモ解決!勉強ブログ
2025.11.04
昨年度の南中3年生の過去問分析!~2学期中間編~
こんにちは!英才個別学院 井土ヶ谷校の室長の原です!
今回は「昨年度の南中3年生・9月定期テスト」の内容をもとに、
どんな力が問われ、どう対策すべきかを分析しました。
第1〜4問:計算と平方根の精度
最初の大問は、四則計算や平方根(ルート)の整理など、基本計算が中心でした。
ただし単純な暗算ではなく、「途中式をどれだけ正確に扱えるか」が勝負。
たとえば平方根の中を分解して簡単にする、分母を整数に直す(有理化する)といった操作を、
丁寧に書ける生徒ほど高得点につながっています。
ポイントは、
同じルートの形をそろえてまとめる
途中式を省かない
この2つです。
第5〜6問:図形と平方根の融合
次に、体積や辺の長さを平方根を使って求める問題が登場。
つまり「図形公式」と「ルート計算」を同時に扱う力が問われました。
ここでは、体積や面積を出すだけでなく、
「未知の辺の長さを逆算する」ような問題がポイント。
立体図形の問題で平方根を含む式が出てくる場合は、
まず落ち着いて“どの部分が平方根になるのか”を把握しましょう。
第5〜6問:図形と平方根の融合
次に、体積や辺の長さを平方根を使って求める問題が登場。
つまり「図形公式」と「ルート計算」を同時に扱う力が問われました。
ここでは、体積や面積を出すだけでなく、
「未知の辺の長さを逆算する」ような問題がポイント。
立体図形の問題で平方根を含む式が出てくる場合は、
まず落ち着いて“どの部分が平方根になるのか”を把握しましょう。
第7〜9問:因数分解と二次方程式
中盤では「展開」「因数分解」「二次方程式」がセットで出題。
ただの計算ではなく、“式の構造”を理解できているかが試されました。
特に、解の関係から文字の値を求める問題などは
「どの数が足し算・掛け算の関係にあるか」を整理できるかがカギ。
ここは“パターン暗記”ではなく、“なぜそうなるか”を理解する必要があります。
第10〜12問:関数×図形×文章題
ここが最も差がついた範囲だと思います。
一次関数のグラフ上に点を取り、座標や面積を求める問題
連続する整数を使った文章題
そして正方形の中を動く点の面積変化など
いわゆる「思考力問題」が集中しました。
特徴的なのは、すべての問題が「式を自分で立てる」形式になっていることです。
式を立てるには、
条件を整理する
どの値を文字に置くか決める
図や関係をもとに式を作る
という3ステップを丁寧に行う力が必要です。
ここが弱い生徒は“式の最初の1行が書けない”傾向があるので、
解答だけでなく立式の練習を意識的に行うのが効果的です。
第13〜14問:比例・反比例・二次関数の基本
後半は「関数の種類を見分ける」「式の特徴を読み取る」内容でした。
比例・反比例・二次関数の違いを、グラフや表を通して理解しておくことが重要です。
また、二次関数では、数値を代入して“係数の値”を求める問題もありました。
見た目はシンプルでも、関数の性質(上に開く・下に開く・対称な形)を理解していないと解けません。
グラフを実際に描いて、形と動きをセットで覚えるのが近道です。
💡まとめ:南中のテストが問う3つの力
1️⃣ 計算の精度(符号・平方根・分母処理)
2️⃣ 図形と関数の関係を整理する力
3️⃣ 式を自分で立て、筋道立てて考える力
南中のテストは、単なる“作業型の数学”ではなく、
「なぜそうなるのか」を説明できる思考型の数学にシフトしています。
📍英才個別学院 井土ヶ谷校では、
一人ひとりの解答の流れを分解して、「どこで思考が止まるか」を対話式の授業でチェックしていきます!!